
写真は「怠けてなんかない! 2」です。
書評「怠けてなんかない! ディスレクシア~読む書く記憶するのが困難なLDの子どもたち」1,2 品川 裕香
はじめての方が、LD、ディスレクシアについて学ぶ最適の本
少し古い本ですが、「LD(学習障害)って何」「ディスレクシアって何」と初めて興味を持った方が読むのに最適な本です。お子様がLDと診断された方、あるいは教職志望の学生さんにもぜひ読んでいただきたい本です。
1,2でLDの人の典型的な症状のほとんどの例がカバーされていると思います。LDの人たちにとっては、普通の人にとって当たり前の「読む」「書く」という作業がこれほどまでの苦行となるのか、と愕然とするかもしれません。そしてほとんどの当事者が、自分の苦しみを他人に理解してもらうことが出来ずに孤独と挫折感を味わってきたことを知るでしょう。
「発達障害」という言葉が今ほどは一般的になる前の時代、多くのLD当事者が周りの人々の無理解に苦しんできたことを思うとつらいものがあります。
一人一人違う
LDと言っても、ひとりひとりそれぞれ症状が違うことが読んでいただければわかると思います。
- 字が読めない人。
- 字は読めるけれども書けない人。
- 字は書けないが、タイピングはできる人。
- 字が左右もしくは上下反転して見える人。
- ワーキングメモリが少なくて覚えられない人。
- 吃音などを併発している人。
などいろんな人がいることがわかります。これでも実際のごく一部の例です。
多くの人が挫折感、孤独感を抱えている
本をよんでいただければ分かる通り、多くの当事者の方は多かれ少なかれ、勉強や生活で数多くの挫折を感じています。他の人にとっては当たり前のことができなかったり理解できなかったり、という経験を繰り返すことで屈辱感を感じていることが多いです。そしてそのことをなかなか他人に理解してもらえないということで、孤独感を抱えていることが多いです。
ですから、LDの当事者と向き合う上では、すぐに結果を求めるよりもまずは本人の傷を癒やすことのほうが先決であることが多いです。
そして、「自信をつける」ということが大事なことであるのがわかります。どんな小さなことでもいいので、「成功体験」を当事者にもってもらうことが大事です。
誰にでも効く解決法はない
発達障害全体にも言えるのですが、特にLDは「誰にでも効くやり方」というのはありません。一人一人対処法は違います。
この本にも何か画期的な治療法が記載されているわけではありません。(そのようなものを期待して本書を読んだ方はがっかりされるかもしれません。)
ADHDタイプの人なら、人によってはコンサータやストラテラのような薬が効く人もいますが、LDの人にはあまりそういうものはないようです。
弱点を補うための引き出しを用意する
現時点でLDの当事者にとっては、完全にその症状をなくす方法を探すよりも、道具やIT機器を使ってその弱点を補うようにすることのほうが現実的な感じがします。(これは本書の内容ではなく私の主観です。)
例えば、作業や勉強を助けるアプリを使うというのも一つの手です。
他人様のサイトですが、そのようなアプリを紹介しているサイトがありました。
キートン・コム
http://blog.keaton.com/2012/09/apps-for-students.html
http://blog.keaton.com/2014/10/apps-for-kids-2014.html
音声でスケジュール管理
昔テレビで見た当事者の方は、スマホの音声認識ソフトに音声入力してスケジュール管理をしていました。現在はSiriなどがあるので、より当事者にとっては使いやすくなっていると思います。
デイジーポッド
私が以前教えていた生徒さんには、授業のときにPCにデイジーポッドという音声読み上げソフトを入れて、教科書を音声読み上げさせていました。(今の若い人なら、「ゆっくり」などの機械音声を聞くのに慣れ親しんでいる人も多いでしょう。)

まとめ
まとめると、
- LDと言っても、一人ひとり違う。
- 多くの人が挫折感、孤独感を抱えている。場合によってはまずそのことを癒やして上げるほうが結果を出すよりも先。
- 上記から本人の「自信をつける」のが先。
- だれにでも効く完全な解決法はまだない。ADHDのようにコンサータがあるわけでもない。
- それよりは現在のIT機器を使って弱点を補うことを考えたほうがいい。
- アプリなどを使う 例:デイジーポッド
といったところでしょうか。
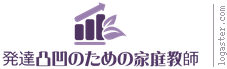





Pingback: LDの人のための学習補助ソフト 「デイジーポッド」について